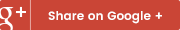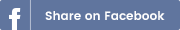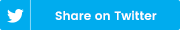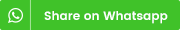秋の帰省とお米愛
みなさま、こんにちは。私は先日、越後三山の麓にある米どころの故郷に帰省してきました。
今回は、相次ぐ熊の目撃情報と雨続きの天候もあり外出は控えめにし、外の景色を眺めながら炬燵でゆっくり過ごす時間が殆どでした。(10月下旬はもう炬燵が出されます。)窓の外には雪囲いの済んだ庭木、色づく山々、そしてどこまでも続く田んぼ。「熊いないよね?」と辺りを眺めても、視界のほとんどを占める田を見ると、熊のことよりもつい令和の米騒動や米農家のことを考えてしまいました。
私の父は数年前米農家を引退しました。父が現役の頃は長く続いた減反政策の真っただ中で、米を作りたくても作ってはいけない田がありました。そして、日本人の米離れ、肥料や燃料の高騰、気候変動など様々な問題が後継者不足にも繋がり我が家の米作りも父の代で幕を下ろすことになりました。現在、代々続いた我が家の田は、後継者のない田を借り上げて米を生産する地元企業にお任せしています。寂しいですが仕方ありません。
米どころとして知られる地域ですがそんな後継者のいない田は多く、そういった企業は多忙のようです。そして最新の大型機械やドローン導入、インターネットでの宣伝や販売など近代的な技術を駆使しながら多大な努力を重ねています。
「何も無いけど米なら余るほどある」、そんな地域で育ちお米が不足するなど考えたこともなかった私ですが、この令和の米騒動で改めてお米の有難さを実感しました。米作りはいくら機械化が進んでも自然相手の重労働、生産者の方々には本当に感謝です。米一粒には七人の神様が宿ると言われていますが、諸説ある中で、水、土、風、虫、雲、太陽、の六つの自然、そして米を育てる人、これらを神に例えたという説があります。今後もその生産者を含めた七人の神様への感謝を忘れずお米をいただこうと思います。そして、生産者と消費者双方にとってより良い米市場が築かれるよう政治の力にも期待したい、そんなことを考えた秋の帰省でした。