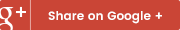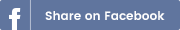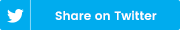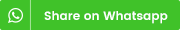やっと秋になりました
こんにちは、院長の阿部哲夫です。
最近の明るい話題といえば、何といってもドジャースの優勝でしょう。大谷選手はポストシーズンに入り、ついに本格的な二刀流が復活しました。ポストシーズンで2勝目を挙げた日にホームランを3本放つなど、その活躍は大リーグ史上、永遠に語り継がれることでしょう。打者としても一流、投手としても一流――私たちの世界でいえば、研究も治療も一流というところでしょうか。もちろん医学界にも研究と臨床の両方に優れた医師はいますが、「研究は素晴らしいが臨床は苦手」あるいは「治療は素晴らしいが研究は苦手」という方のほうが一般的かもしれません。まさに「天は二物を与えず」といったところでしょう。
先日、当院とエーザイの共同開催で講演会を実施しました。荒川区や荒川医師会の後援をいただき、医師会員、区役所職員、包括支援センター、介護事業所職員、ケアマネジャーなど、多くの方々にご参加いただき盛会となりました。この講演会は、当院が東京都から認知症疾患医療センターの指定を受けて10年の節目を迎えるにあたり、記念講演会として開催したものです。私からは、開業以来の認知症治療の歴史と当院の変遷についてお話させていただきました。
講演の中では、いわゆる団塊の世代が後期高齢者となる「2025年問題」にも触れました。この10年間で認知症の有病率や患者数は、当初予想されたほど増えていないという統計データも示されています。高齢者の総数は増加しているにもかかわらず、認知症患者数が大きく増えていないのはなぜでしょうか。ひとつは、この10年間、認知症の問題が広く取り上げられるようになり、多くの方が予防に努めてきたことが挙げられます。日常的な運動や社会交流を意識して続けるなど、高齢者一人ひとりの意識向上がプラスに働いたのだと思います。もうひとつは、早期発見・早期治療の進展です。以前は「年のせい」とされて放置されていた認知症が、病気として認識されるようになり、早期診断・早期治療につながるようになったことも要因でしょう。
これからの認知症対策では、さらに「予防」に重点を置くことが重要です。発症して脳神経が傷害されてからでは、対策にも限界があります。従来の運動や人との交流といった予防法に加え、発症前にレカネマブやドナネマブといった薬剤を使用して発症を抑制する取り組みも、今後は広く行われるようになると思います。現在は薬剤が高価であることや、導入に必要な検査の負担が大きいことから、投与対象は一部の患者さんに限られています。しかし、今後は検査の簡略化や投与方法の改善が進むと予想されていて、10年後にはより一般的な治療となっているかもしれません。こうして考えると、認知症対策の未来は決して暗いものではないと思います。
気がつけば、当院が認知症疾患医療センターに指定されてから早くも10年が経ちました。大谷選手ほどではありませんが、私も「診療」と「経営」の二刀流でこの10年間を走り抜けてきました。この大役をなんとか果たしてこられたのも、患者様やご家族様をはじめ、行政の皆様、包括支援センター、介護事業所、地域の医療機関、そして院内スタッフなど、多くの方々のお力添えのおかげです。この場をお借りして、心より御礼申し上げます。「ありがとうございました。」